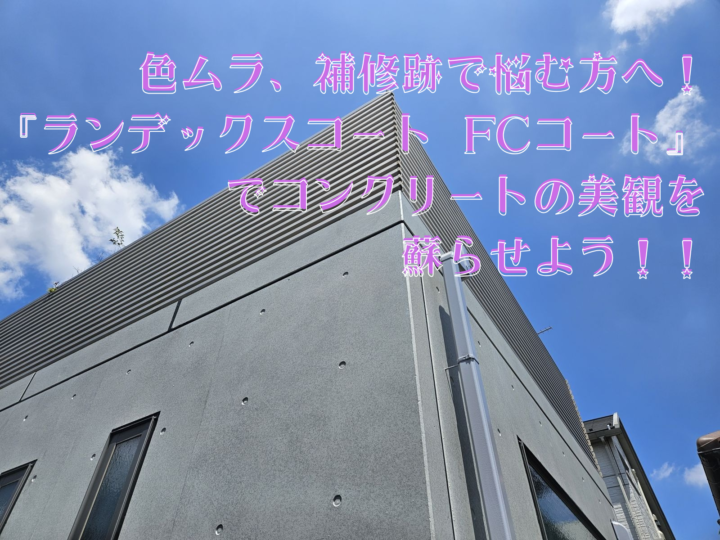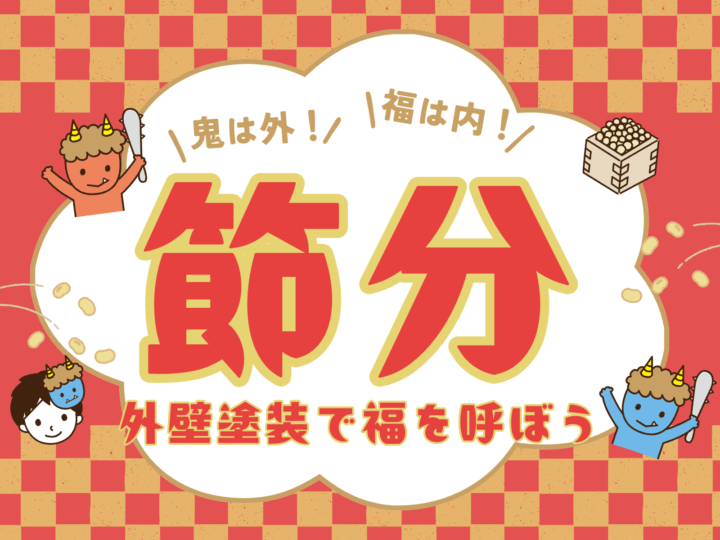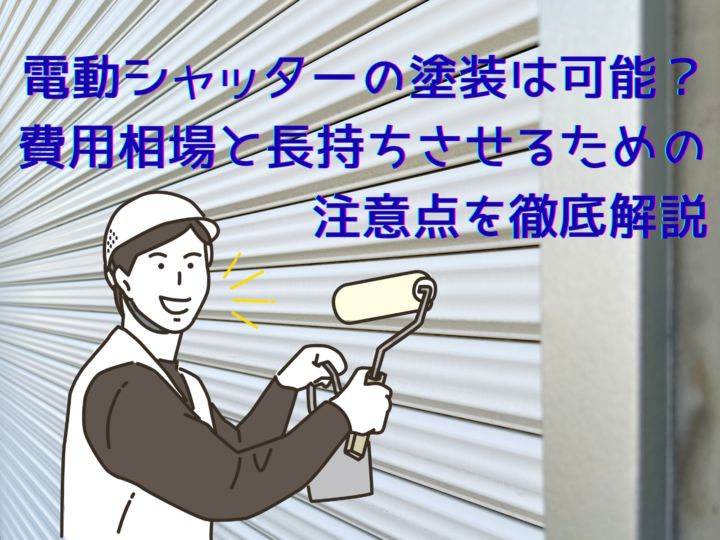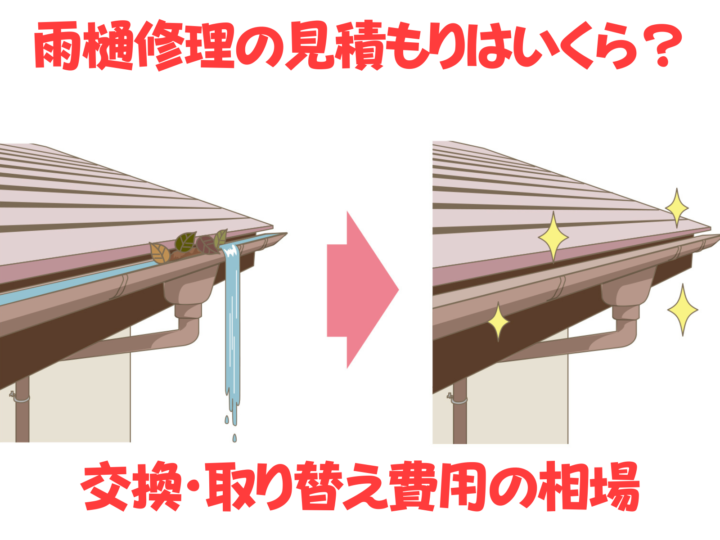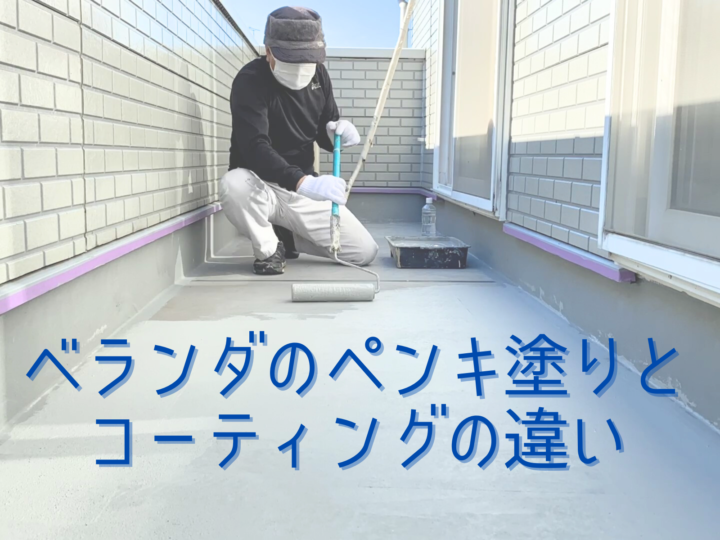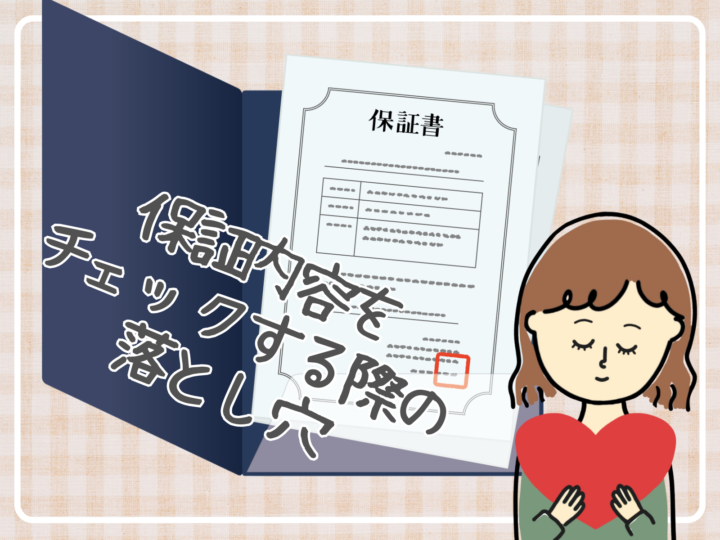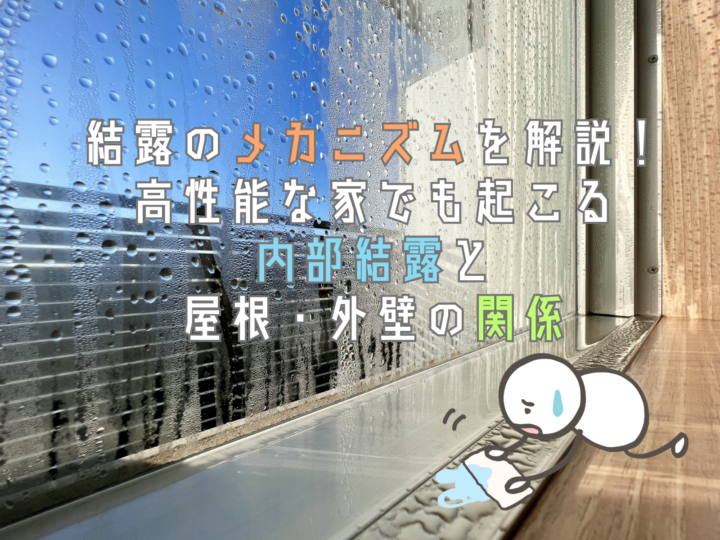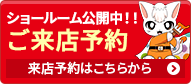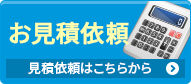ジョリパット施工価格と特徴|デザイン性と耐久性のバランス꒰ 🐈⬛ ♫ 彡
外壁塗装を検討している方の中には、「ジョリパット」という仕上げ材を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。 ジョリパットはアイカ工業が開発した高性能の左官材で、塗装と仕上げを兼ねた外壁仕上げ材として根強い人気を誇ります🥖.˚ ୭ モルタル外壁やサイディングとは違った「質感のあるデザイン」が魅力で、建築雑誌や注文住宅の施工例でもよく見かけます。 とはいえ、実際に施工を検討する段階で「価格はどのくらい?」「本当に耐久性があるの?」と疑問を持つ方も多いはずです。 そこで今回は、ジョリパットの施工価格の目安や特徴、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます!! 引用:アイカ工業株式会社 ジョリパットとは? ジョリパットは、樹脂系の仕上げ材をコテやローラーで塗り、さまざまな模様や質感を表現できる外壁材です。 一般的な塗料は「平滑に塗る」のが目的ですが、ジョリパットは「模様をつける」ことを前提としているため、 デザイン性が非常に高いのが特徴です。 外壁の他にも、内装のアクセントウォールとして使われることもあり、住宅の雰囲気を大きく変える力を持っています。 ジョリパット施工価格の目安 気になる施工価格について、一般的な目安を整理してみましょう。 1㎡あたり:約3,000円〜5,000円 30坪住宅(外壁面積150㎡程度):約45万〜75万円 ※あくまで材料費+施工費の相場感であり、下地の状態やデザインの複雑さによって変動します。 通常のシリコン塗料による外壁塗装が1㎡あたり2,000〜3,000円程度であるのに対し、ジョリパットはやや高めです。しかし、模様仕上げという「デザイン料」が含まれていると考えれば納得できる価格帯といえます。 ジョリパットのメリット ジョリパットが人気を集める理由は、デザイン性だけではありません。ここでは代表的なメリットを紹介します。 1. デザインの自由度が高い コテやローラー、吹き付けなど多様な施工方法があり、数百種類のパターンを表現できます。和風からモダン、ナチュラルまで、好みに合わせたオリジナルの外観を作れるのは大きな魅力です。 2. 耐候性・耐久性に優れる ジョリパットはアクリル樹脂を主成分としており、一般的なモルタル仕上げに比べて耐久性が高いです。適切にメンテナンスすれば15〜20年の耐用年数が期待できます。 3. メンテナンス性の良さ 万が一部分的にひび割れや欠けが起きても、その箇所だけを補修しやすいのが特徴です。サイディングのように一面交換が必要になるケースと比べて、コストを抑えられる場合があります。 4. 汚れが目立ちにくい 表面がざらついているため、平滑な外壁と比べると多少の汚れは目立ちにくいという利点があります。 ジョリパットのデメリット もちろん、ジョリパットにも弱点があります。施工を検討する際は、メリットと合わせて理解しておくことが大切です。 1. 汚れやカビが付着しやすい 表面に凹凸がある分、ホコリや雨だれが溜まりやすく、年月が経つと黒ずみやカビが出やすくなります。定期的な洗浄や防汚タイプの仕上げを選ぶことが重要です。 2. 施工費が高め 一般的な外壁塗装に比べると施工価格は高く、さらに複雑な模様を選ぶと職人の手間が増えるためコストが上がります。 3. 職人の技術に左右されやすい ジョリパットは左官仕上げのため、職人の腕によって仕上がりの差が出やすい素材です。経験豊富な施工店を選ばないと、期待したデザインにならない可能性があります。 4. 再塗装時の注意点 将来、外壁を塗り替える際には表面の凹凸が障害となる場合があります。適切な下地処理を行わなければ密着不良を起こすリスクもあるため、専門知識がある業者に依頼する必要があります。 ジョリパットの施工が向いているケース どんな建物にジョリパットが適しているのか、具体的なケースをまとめてみました。 デザイン性を重視したい住宅:シンプルな外壁に個性を与えたい方に最適。 高級感や重厚感を演出したい場合:高級住宅や店舗の外観に使うと存在感が増します。 部分使いでアクセントをつけたい場合:外壁全体でなく玄関まわりやバルコニーだけに施工するのも効果的。 逆に、コストを最優先する場合や「汚れが気になる環境」では不向きな場合もあります。 メンテナンスのポイント ジョリパットを長持ちさせるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。 5〜10年ごとの点検:ひび割れや剥がれがないかを確認。 高圧洗浄での清掃:付着した汚れやカビを定期的に除去。 トップコート仕上げの検討:防水性や防汚性を高めるためにトップコートを塗布するケースもあります。 施工業者選びの重要性 ジョリパットは施工技術が仕上がりを大きく左右するため、業者選びが非常に重要です。選ぶ際のポイントは以下の通りです。 ジョリパット施工の実績が豊富か 仕上がりサンプルや施工写真を確認できるか アフター保証や定期点検の体制があるか 「安さ」だけで決めると、仕上がりがイメージと違ったり、数年で劣化が進んでしまうこともあります。必ず複数社に見積もりを依頼して、内容と価格を比較検討しましょう。 まとめ:デザインと耐久性の両立を目指すならジョリパット ジョリパットは、デザイン性と耐久性を兼ね備えた魅力的な外壁仕上げ材です。 価格相場:1㎡あたり3,000〜5,000円 メリット:デザイン自由度が高い、耐久性がある、部分補修しやすい デメリット:汚れやすい、施工費が高め、職人の技術差が大きい 「他の住宅と違う個性的な外観にしたい」「長く愛着を持てるデザインにしたい」という方におすすめです˚🚜⊹ ただし、コストや汚れの問題を理解した上で、信頼できる施工業者に依頼することが成功のポイントといえるでしょう💡 👉 外壁デザインにこだわりたい方は、まずはジョリパットの施工実績が豊富な専門業者に相談してみてください。 実際の仕上がりを確認することで、自分の理想の住まいに近づけるはずです。 お問い合わせはこちら 2026年02月14日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識
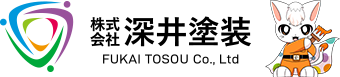
 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 LINEかんたん相談
LINEかんたん相談