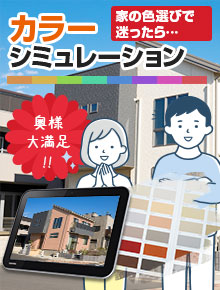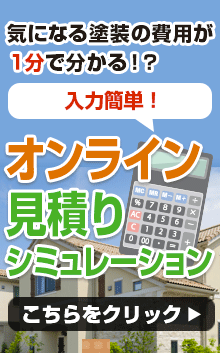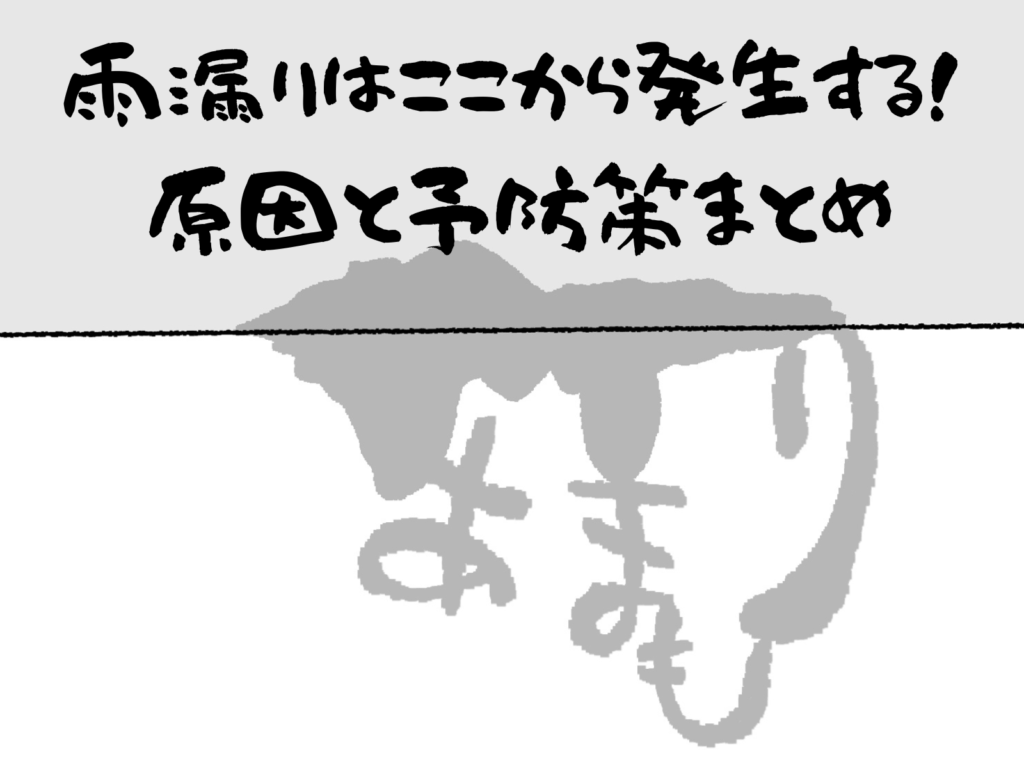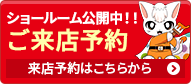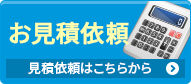雨漏りの8割は同じ場所から?知らないと損するチェックポイント.☝️•.
こんにちは、地域密着で外壁・屋根のメンテナンスに取り組んでいる深井塗装です°🐇⌗𖦹
「突然の雨漏り、どこから水が入ってくるのか分からなくて不安…」
そんなお悩みをお持ちではないでしょうか?実は雨漏りの原因は意外と共通している部分が多く、
適切な知識を持っていれば事前に防げるケースも少なくありません!
今回の記事では、プロの現場経験から分かる「雨漏りの発生しやすい箇所」と、その効果的な予防方法を詳しくご紹介します。
読んでいただければ、「我が家のこの部分は点検しておいた方がいいかも」といった気づきが得られるはずです࿁ 🥐⏜ ࣪
これから外壁や屋根のメンテナンスを検討している方はもちろん、
既に雨漏りを経験して修理をしたけれど再発が心配…という方にもぜひ読んでいただきたい内容です。
目次
雨漏りが発生しやすい代表的な場所
屋根の棟板金(むねばんきん)
屋根の頂上部分を覆う棟板金は、風雨や紫外線の影響を強く受ける場所です。
固定している釘が緩むと隙間ができ、そこから雨水が侵入してしまいます。
特に台風や強風の後に不具合が見つかるケースが多く、定期点検の重要性が高い箇所です。
外壁とサッシの取り合い部分
窓まわりは雨漏りの発生率が非常に高いポイント。
外壁とサッシの間に打ち込まれているシーリング材が劣化すると、ひび割れや剥離が起こり、そこから水が入ります。築10年以上経過している住宅では特に注意が必要です。
ベランダやバルコニー
防水層の劣化によって雨水が内部に浸入するケースが多く見られます。
排水口が詰まって水が溜まると、防水シートの劣化が早まり、やがて雨漏りにつながります。
外壁のひび割れ
一見小さなクラックでも、放置すると雨水が毛細管現象で内部へ侵入します。ひび割れは早期発見・早期補修が鉄則です。
雨漏りの原因は「経年劣化」が大半
「うちは手抜き工事だったのでは?」と不安に思われる方もいますが、実際には経年劣化が原因の雨漏りが大半です。
特にシーリング材や防水層、塗膜といった部分は紫外線・雨・風に常にさらされており、10年〜15年で寿命を迎えるのが一般的です。
つまり「どんなに丁寧に建てた家でも、適切な時期にメンテナンスを行わなければ雨漏りのリスクは避けられない」ということです。
n
雨漏りを予防するための具体的な方法
1. 定期点検を行う
築10年を超えたら、専門業者による点検を定期的に受けるのが理想です。特に台風や大雨の後は、早めに点検を行うことで小さな劣化を見逃さずに済みます。
2. シーリングの打ち替え
外壁とサッシの取り合いや外壁目地のシーリングは、10年前後での打ち替えが目安です。新しいシーリング材に交換することで雨水の侵入を防げます。
3. 屋根のメンテナンス
棟板金の釘をビスに打ち替えたり、屋根材の塗装・カバー工法を行うことで雨漏りリスクを下げられます。屋根は自分で点検しにくいため、ドローン調査や専門業者の目視点検を依頼するのが安心です。
4. 防水工事の定期更新
ベランダやバルコニーの防水は、10〜12年ごとに再施工するのが目安です。ウレタン防水やFRP防水など、それぞれの工法に合わせて適切な時期にメンテナンスを行いましょう。
雨漏りを放置するとどうなる?
「ちょっと天井にシミがあるだけだから大丈夫」と放置すると、内部でカビや腐食が進み、構造体そのものを傷めてしまいます。
結果として大規模修繕が必要になり、修理費用は数十万円〜数百万円に膨らむことも。
早期に補修すれば数万円で済んだ工事が、放置によって何倍ものコストになるケースは珍しくありません。
プロが伝えたい雨漏り対策の考え方
-
雨漏りは「起きてから対処」では遅い
-
小さな劣化のうちに補修することで被害を最小限にできる
-
定期的なメンテナンスは「費用がかかる」のではなく「無駄な出費を減らす」行為
これが、外壁・屋根の施工現場を数多く経験してきた私たちが実感している事実です。
まとめ
雨漏りの多くは「屋根の棟板金」「外壁とサッシの取り合い」「ベランダ防水」「外壁のひび割れ」といった、
共通のポイントから発生します。これらはすべて、定期的な点検と早めのメンテナンスで防ぐことができます🐾⟡⟆ ྀི
深井塗装では、雨漏り診断から補修、外壁・屋根の塗装や防水工事まで一貫して対応可能です。
経験豊富な自社職人がしっかりと点検・施工を行い、お住まいを長く守ります。
「雨漏りが心配…」「築10年を超えたけれど点検をしていない」という方は、ぜひ一度ご相談ください!
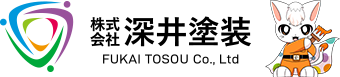
 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 LINEかんたん相談
LINEかんたん相談